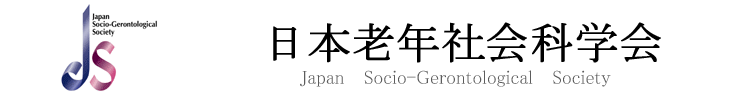更新日 2026/1/20
- ヘルスコミュニケーション;原子力災害・コロナ禍がもたらした「未知なる不安」を乗り越える
- 安村誠司編著
- ワールドプランニング
コミュニケーションに関する環境は,情報の媒体が多様化し,双方向性の情報交換が行われるようになった今日,急速に変化してきている.そのようななかで,フェイク情報の拡散,リテラシー格差による情報の偏りなどの社会状況も生じており,コミュニケーションに関する課題は,日常生活から政治,経済,国際関係まで広範にみられるように思われる.
本書は,健康に関連するコミュニケーションの問題が顕在化した原発事故とCOVID-19 をとおして,ヘルスコミュニケーションに焦点を当ててまとめられたものである.従来から知られているリスクコミュニケーションやクライシスコミュニケーションは,リスク時やそこで生じる危機が発生した際に行われるコミュニケーションである.これに対してヘルスコミュニケーションは,健康の維持向上という結果に注目して,健康情報を容易に理解し行動できるような支援を目指すコミュニケーションへの改善という要素を含んでいるということであり,本書には,災害時や感染流行時の課題をとおして,通常時にも役立つ健康に関する望ましいコミュニケーションの情報が盛り込まれている.
本書は,2023 年に開催された第15 回日本ヘルスコミュニケーション学会学術集会におけるシンポジウムの内容をまとめたものである.原発事故とCOVID-19 感染流行の際に共通する「未知なる不安」への対応と,今後の健康リスクに関する章と,ヘルスリテラシーからヘルスコミュニケーションという4つの章から構成されている.前半の3つの章は,原発事故やCOVID-19感染流行と,そこで生じたさまざまな事例や課題が詳細に述べられている.こうした災害や感染流行時におけるヘルスコミュニケーションでは,提供側の課題に加えて,正しい情報の選択とアクセスという受け手側のリテラシーの向上と,そのための支援が不可欠であることが理解できた.また,感染流行時の正誤の混在した情報の増幅としてのインフォデミックは,スマートフォンやソーシャルメディアが普及することにより,感染流行時以外にも広がっており,デジタルリテラシー向上のために,操作性スキルをはじめとする6 つのスキルが必要であることも実感できた.これをふまえた第4章では,コミュニケーションは,患者の健康アウトカムに影響する医療の原則であることなどのコミュニケーションの重要性や意義などが述べられている.アクセス可能であることなどのWHO の効果的なコミュニケーションのための6つの原則も,健康に関するコミュニケーションの基本として参考になった.
本書は,副題にもあるように,原子力災害・コロナ禍がもたらした「未知なる不安」を乗り越えることを主題としてまとめられている.その主旨は充分に達成されているが,加えて,災害や感染流行時以外にも,保健・医療・福祉においてヘルスコミュニケーションとその展開が重要であることが,説得力をもって明示されており,多くの関係者の刺激となることが期待される.
更新日 2025/10/20
- 比較福祉社会学の展開;ケアとジェンダーの視点から
- 西下彰俊編著,何 妨容,山口佐和子,乙部由子,加藤典子,嶋守さやか著 定価3,080円
- 発行:新評論
本書は,若年者や高齢者の「ニーズ」と「ケア」を軸に,異なる専門領域の6名の研究者による共同研究の成果である.社会保障制度の整備が不十分な状況下で,脆弱な人々のニーズが満たされていない現実に着目し,問題解決への方向性を示している点に意義がある.
第1 章では,日韓両国の介護保険制度を比較し,日本の家族介護慰労金と科学的介護情報システム(LIFE)に焦点をあて,介護慰労金廃止やADL ジレンマを指摘した.韓国の長期療養保険制度においては,「家族の社会化」の問題点を指摘している.第2 章では,老々介護に焦点をあて,日本のケアマネジャー調査からは,老々介護者の問題を指摘した.韓国の療養保護士(訪問ヘルパー)の調査により,老々介護と療養保護士の扱い方を指摘している.
第3 章では,離婚後の親権問題をジェンダーの観点から,DV 被害者の負担の複雑化と新たなジェンダー不平等を生む制度の矛盾を指摘し,日本文化に基づいた支援体制の必要性が示された.第4章では,新型コロナウイルス感染症拡大が女性労働者に与えた影響を分析し,非正規雇用の若年女性が影響を受けているが,「飲食サービス業」に集中する傾向があり,既存のフェミニズムでは説明できない未婚女性の労働実態を明らかにした.
第5 章では,単身高齢者世帯が抱える問題を論じ,単身高齢女性は貧困に陥りやすく,単身高齢男性は日常生活スキル不足で日常生活に支障が生じやすいことを指摘し,地域包括ケアシステムの構築の必要性を指摘した.第6章では,路上生活者への支援を取り上げ,山谷における路上生活者とボランティア活動者との「仲間」関係は,社会保障制度の隙間を補っている関係であることを示した.
本書は,日韓における介護保険制度の問題や課題を明らかにし,社会保障制度だけでは対応困難な脆弱層のニーズへの解決策を提示している.「住み慣れた地域で住み続ける」という理念のもとで進む社会保障制度の改革が,ニーズ解決のためのサービス利用が申請主義であるため,「住み慣れた自宅や路上でニーズが満たされていない」という現実を生み出しており,個人化の進行が個人に責任転嫁される状況が生じている.社会保険料の納付が義務であるのと同様に,個々人のニーズに基づいたサービス利用を義務とする「脱申請主義」への転換によって,だれもが安心して自宅で人生の最終段階を迎えられる社会システムへの改革が待ち望まれる.一方で,本書は共同研究者による執筆のため,各章の分析にばらつきや理論的一貫性の問題や課題がある.それでも本書は,日韓の介護保険制度や社会保障制度に関心をもつ研究者,ボランティアラー,政策立案者にとって貴重な良書である.ケアの社会化とジェンダー平等という視点から,今後の研究発展に資する良書である.
更新日 2025/4/20
- フレイル・ロコモのグランドデザイン
- 日本医学会連合 領域横断的連携活動事業(TEAM事業)「フレイル・ロコモ対策会議」編集 定価4,400円+税
- 発行:日本医事新報社
「フレイル・ロコモ対策会議」の活動のひとつとして刊行された書籍で,フレイル・ロコモの基礎的内容から応用的内容まで,領域横断的に幅広く解説がなされている.
全7章で構成され,第1章はフレイル・ロコモの概念や疫学,第2章は老化に伴う臓器の機能低下とフレイル・ロコモとの関連性,第3章はフレイル・ロコモに関する基礎医学的知見・ロボット技術・ICT・IoTなどの先端技術,を概説している.第4章はフレイル・ロコモの予防と介入について,運動,栄養,社会活動の観点からの方法論について概説しているだけでなく,医療現場,介護現場,自治体事業などさまざまな現場における予防や介入についても触れられており,フレイル・ロコモの予防や介入を幅広い視点でとらえることに役立つかもしれない.
第5章は,臓器別に疾患とフレイル・ロコモとの関連が概説されている.また,第6章では,高齢者に起こりやすい,排尿・排便障害,褥瘡,転倒,視覚障害,難聴などの問題についても触れられている.第2章,第5章,第6章は,医学系研究者や高齢者の診療に携わる医療従事者において,研究や日常診療において参考になるかもしれない.
第7章では,フレイル・ロコモ対策における包括的ケアについて概説され,緩和ケアについても触れられている.フレイル・ロコモを有する高齢者の緩和ケアについては今後の発展が期待される.本書は,医学的観点からの解説が多く,介護福祉領域における活用には限界もあるように感じる.しかし,すべての医療従事者がフレイル・ロコモに対する知識をもって高齢者のケアにあたることは重要なことであり,本書がさまざまな領域の医療従事者がフレイル・ロコモに注意を向けるきっかけになることを期待したい.